- Home
- しゃちょーのブログ, 俳句
- けやき俳句会合同句集Ⅳ
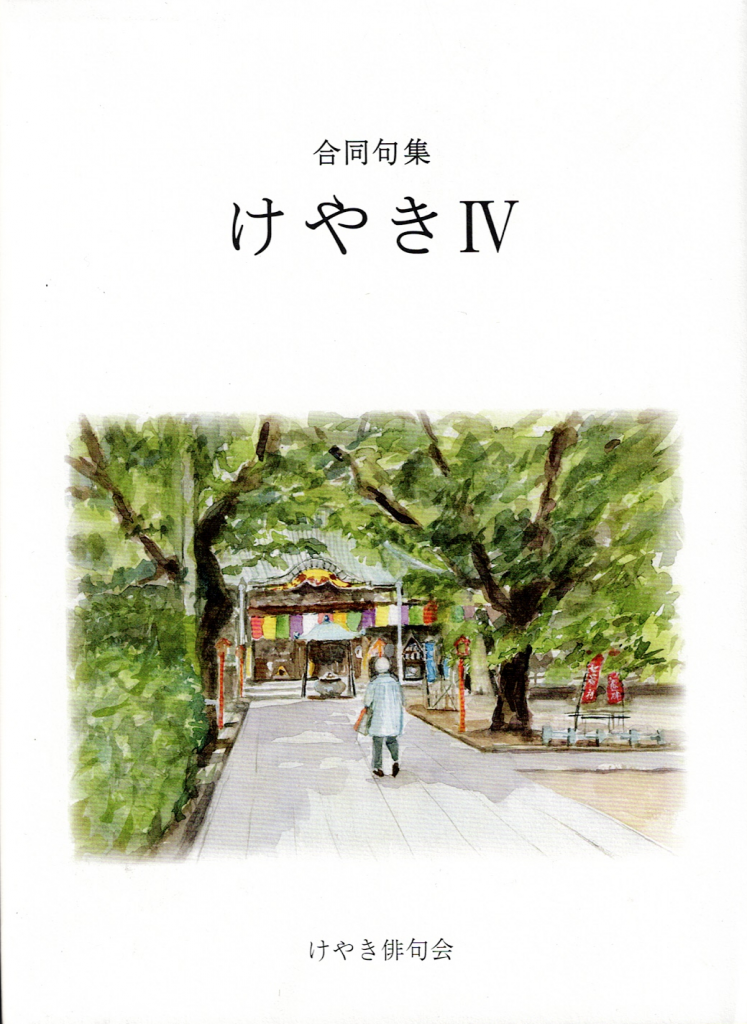
川越のけやき通りにちなんで名づけられたけやき句会の「けやき俳句会合同
句集Ⅳ」をお送りいただき楽しく拝見させていただきました。
誠実に俳句や人生に向かわれていることを感じられました。
私も所属する明日香句会の句友の方もいらっしゃり、せっかくの句に感想を
伝えたく鑑賞文を書いてみました。
私が句会で選んだ句も掲載されていました。
明日香句会の句友の方が多くどうしてもその方々の句を多く選んでしまい
ました。
悪しからずご了承ください。
けやき俳句会合同句集Ⅳ 選句松橋晴
「遠花火」 小沢弘一
冠の傾ぎをなほす雛の朝
春うららトイレの壁の世界地図
草木瓜や堂塔跡の大礎石
星空へ根を張るごとし冬木立
括られて色まさりけり寒の菊
コンセント抜かれし朝の聖樹かな
日常のさりげない一こまを切りとってそこに意味づけをするのではなく、
視点の角度によって物事の本質に迫っています。俳句の本質を捉えて
います。
春風や牛の睫毛の藁ぼこり
ばら園の空へホースの水の玉
ズームアップの力で技術や作意を感じさせずに読むものをこの世界に
引き込みます。結果作者の感性のきらめきに同調します。
風鈴のきれいな風と出逢ひけり
髪ほどくゴム輪手首へ遠花火
もっとも惹かれた二句です。音韻の美しさと、映像美の極みです。
「夏座敷」 佐野静子
囀りや笑へて泣ける紙芝居
春爛漫歩きスマホを牛蒡抜き
穏やかな言葉遣いで丁寧に日常が切り取られています。多くの方に
届く句だと感じました。
頃合いの風を掴みて初つばめ
瓶漬けのスティック野菜藍浴衣
冬の鵙庭師のはしごぐんと伸ぶ
時折音韻の力が明白なしっかりと題材にピントのあった句に出会います。
たぶん日常は穏やかな方かと想像しますが、その内側には以外に太い
感性が潜んでいるのかもしれません。それも楽しみです。
「木の実降る」 清水晃子
この村をいつか出てやる松の芯
伐採の夜の花守の男泣き
陽炎やおまへが先に鬼になれ
かけひきのできぬ性分冷奴
鶏頭のごとりと当たる蔵の壁
強い言葉で状況を明確に表現し題材を表現するだけでなく、斬りこんで
います。俳句よりは現代詩に近い乾いた感性が面白く惹かれます。
詩であることに挑戦しているようでもあり、ぎりぎりの鬩ぎあいが楽しみです。
「猫の恋」 畠山要子
居酒屋の鏡開きの汁粉かな
過疎村に嫁来る話山笑ふ
黄水仙頷きあはぬ間柄
間の手の入る舟唄夏がすみ
放屁虫囲む童のはかり事
お酒の話題、お酒を飲んでの話題が多くあります。よほど飲むのと話すのが
お好きなのだと推察します。また句も明るく、楽しいものが多く日常の賑わいが
感じられ、こちらも楽しくなります。俳句も幸せな毎日に役立っているのでしょう。
「朝つばめ」 村瀬八千代
「ぶさいくでごめんね」春の雪だるま
朝日さす嶺に一礼耕せり
紙雛男の子ばかりの古き家
衛兵の交代儀式花吹雪
喧嘩して帰った子よりカーネーション
句形のいい句とそうでない句、音韻のいい句とそうでない句がありますが、こち
らは明らかに音韻よりです。見た目は平凡かなと思う句が口承してみると思わぬ
効果を発揮して胸に迫ります。特にA音のリフレインがお好きなようで句にリズム
と活気と実存感をもたらしています。
「木綿のハンカチーフ」 山田賀寿子
背の丈を褒めて年玉渡しけり
宇宙から戻りめあてのチューリップ
まっさきに地震知らせる守宮かな
人を見ぬふりをして見る青蛙
桐の花又桐の花能登路ゆく
日常の生活や周囲の生き物たちを暖かく見つめる視線が感じられます。
「人を見ぬ」の句の青蛙の定まらぬ視線の捉え方に惹かれました。
また「桐の花」は、古くから家に植えて嫁入りの箪笥を作るといわれている桐が
満開で旺盛に育っているのに、地震等の厳しい環境で思うように生活を維持
できない能登の現状が思いやられ胸を打たれます。
「江戸切子」 横松しげる
普段着のままの往生木瓜の花
龍天に昇りし後の脚立かな
七宝に青き十字架風ひかる
十薬や廊下に影を置く薬研
病妻の望む素うどん葱刻む
最愛の方をなくした悲しみと喪失を静かに詠われています。ひと時の激情や
虚脱ではなく決して解消することのなく身体と心の奥底に宿る悲しみは、むしろ
決して忘れないという決意によってしか共に生きることができません。
観戦の妻の歓声缶ビール
絵日傘や少女は羽化をくりかえす
共に生きた時間は、ただ単なる思い出ではなく、自分が生きた証です。
美しく、楽しい時間が言い留められています。
凩や鉄瓶の白湯ほの甘し
オーバーの寝そべってゐるピアノかな
しげるさんの鍛えられた感性の確かさ、的確な把握、長い修練の力を感じ
ます。
尖塔に触るる雨雲畔青む
大の字に眠る夢見る案山子かな
もっとも惹かれた二句です。
私ごときが選評するものではありません。
「冬の虹」 渡辺隆
料峭や人に数多の蝶番
大陸に昔孔孟霾れり
お玉杓子先づは後ろの左足
佃煮のイナゴの五体不満足
知的な発見の面白さで楽しませる句が多くあります。骨の標本のように
蝶番でできた人間。昔は孔子孟子などの知の巨人のいた中国。等々、
隆さんのニヤッとした表情が見えるようです。一種のサービス精神といい
ましょうか。これも俳句の本質のひとつです。
あさま山荘突入の日の受験票
国々におらが富士あり林檎咲く
サイダーや昭和のハレの慎ましき
ラグビーや青春は青春を語らず
時折登場するレトロな昭和の風景。自らの感情を俳句では直接表現しない
隆さんの内の世界が垣間見れます。季語の使い方の上手さに主張をこめて
いるようです。
カップルを蹴って押し出す貸しボート
知らぬ間に取るる瘡蓋涼新た
この二句は音韻の良さで選んでみました。隆さんが音韻を意識して句を
作っているイメージはなかったのですが、こうした句で詩的なイメージを
創出できるのはさすがです。「カップルを」の句のカップルと貸しボートの
KAの頭韻と蹴ってのK音との音の勢いとリズムの良さ。全体に滑らかな
響きの中、瘡蓋と涼新たのTAの脚韻での確実な着地。みごとです。
桜には見せぬ顔して梅見かな
点字なぞる指のふくらみ豆の花
少年の足裏海向く夏座敷
林檎投ぐる放物線の結ぶ仲
告げに来る人のゐる幸冬の虹
知的でクールな句が多い隆さんの句ですが、冷笑的なイメージはありま
せん。シャイで男らしく暖かく人を包むものがあります。日常では一言多い
うるさ方を演じている隆さんの内面からもれて来る光が感じられる句が
いくつかありました。楽しませていただきました。ありがとうございました





